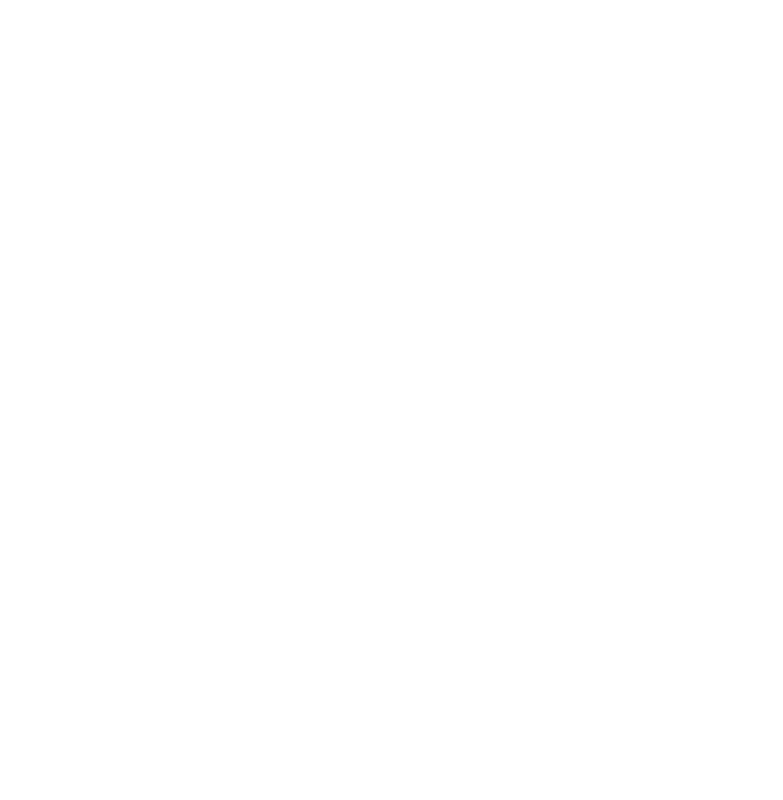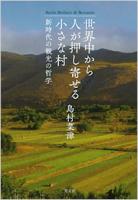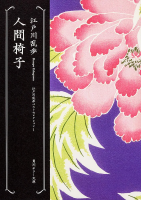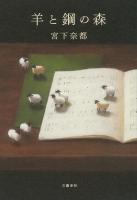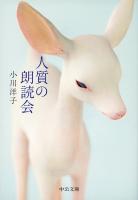龍大生のお薦め本をご紹介いたします。
二葉亭四迷[作] 十川信介[校注] 岩波書店 2004年
深草図書館:和顔館2F開架文庫・新書 081/イワナ/7-1
資料番号:10405050424
瀬田図書館:本館1F文庫 081/イワナ/3-7-1
資料番号:30400050872
本作は一般に「未完の小説」と称されている。にもかかわらず、なぜ現代まで読み継がれているのだろうか。
物語は、主人公・内海文三とその従姉妹のお勢、友人の本田昇という三人を中心に展開していく。文三はお勢に恋心を抱くが、それに心を奪われるあまり職務に身が入らず、ついには解雇されてしまう。以後もお勢への報われぬ想いと、友人である本田への劣等感の狭間で、あがき続ける。
実績がないがプライドが高く、言動には自己愛と嫉妬、そして怠惰が同居している。決して立派な人物とは言い難いが、だからこそ私は、彼の姿に強く共感した。情報が溢れる現代に生きる私たち―常に他者の理想と比べられ、否応なく劣等感と向き合わされる私たち―の姿と、どこか重なるのではないだろうか。
また、本作は言文一致体の祖ともされており、自然な語り口は今なおみずみずしさを失わず、読む者に不思議な心地よさを与えてくれる。
自己肯定感に揺れながらも必死に生きようとする文三の姿は、悩みや生きづらさを感じているときに、きっと心に残るだろう。
文学部1年生 大岩 直樹
平野啓一郎[著] 文藝春秋 2018年
瀬田図書館:本館B1開架 913.6/ヒケア
資料番号:31905030608
「愛にとって、過去とはなんだろう?」本書を通して著者平野啓一郎は私達にこう問いかけています。
この物語は弁護士の城戸を中心に展開され、元依頼人である里枝の亡くなった夫が全く別人の人生を生きていたことが発覚し身辺調査を依頼されるところから始まります。城戸は”ある男”の過去を辿る中で衝撃の事実を知ることになります。
人を愛するのにその人の過去は重要なことなのでしょうか。この物語ではある男の正体を追う上で人間存在の根源について考えさせられますが、最大のテーマは愛です。愛すると言うことは知りたいと言う気持ちから始まるものだと私は考えます。そのため、やはりその人の過去は知るべきことなのではないでしょうか。
ある男とは一体誰なのか、その正体を探る中で人の優しさに触れることが出来る作品だと思います。
心理学部3年生 篠川 倖
『格差と貧困のないデンマーク : 世界一幸福な国の人づくり』
千葉忠夫[著] PHP研究所 2011年
深草図書館:和顔館2F開架文庫・新書 081/ヒエイ/720
資料番号:11100005810
今の自分の生き方は本当に自分で選んだものか。
この著書はそれを強烈に問いかけてくる。日本の学生は「勉強」の目的が曖昧な傾向にある。本来は学びたいことを学ぶために大学へ進学するはずが、大学進学自体が目的となっている人が多い。それは「大卒」が一括りにされ、一つのステータスとして扱われている社会に問題がある。「やりたいことがあるからその道に進みたい」と主張しても、大人に「大学くらいは出ておきなさい」と言われた人もいるのではないか。一方、デンマークは生徒が目的を持って学び、なんとなく大学へ進学することはない。その自主性を育てる教育環境があり、社会全体も寛容である。
この著書は、普段の生活では気づけない「これっておかしくないか?」と考えるきっかけを与えてくれる。「周りがそうしているから自分もそれに従う」という生き方をしてきた人に一度読んでほしい。日本の常識は世界では通用しないかもしれない。
経済学部1年生 奥田 香穂
ハン・ガン[著] きむふな[訳] クオン 2011年
深草図書館:8号館閉架3F 929.1/アタラ-U/1
資料番号:11705038791
この本は、主人公であるヨンへがある日、奇妙な「夢」を見てから肉を受けつけなくなった話から始まります。ヨンヘの夫、義兄、姉の3つの視点を通じて、ヨンへの内面崩壊と社会的抑圧を表します。
ヨンヘは暴力的で疲れきった夢を見た後、肉を食べないと宣言し、これによって家族や社会から理解されず孤立します。その後、ヨンへは義兄の芸術的な欲望の対象になってしまい、結局自分が植物になると言って精神が崩れていきました。
菜食という行為を通じて体に対する自己決定権、そして非正常と烙印を押す社会の暴力性を鋭く表します。 ヨンヘはついに話さないことで抵抗し、「私は植物になりたいです」という言葉で人間世界の暴力から抜け出そうとする切迫した願いを表します。
私たちがどれほど簡単に他人の違いを拒否するのか、また何が正常で非正常なのかを誰が決めるのかを振り返るようになりました。
この小説は語ります。沈黙も抵抗になり得ると、そして違いは決して間違いではないということを。
経営学部4年生 李 秀彬
小池一夫[著] 朝日新聞出版 2018年
深草図書館:和顔館2F開架文庫・新書 081/アサヒ/682
資料番号:11800030326
人は、どうやって生きたら幸せになれると思いますか?
人との心地よい距離感の保ち方、しんどい仕事の乗り切り方、豊かな歳の重ね方。そんな生きていくうえで誰もがぶつかる問いに優しく答えてくれるのが小池一夫さんの『人生の結論』です。
本書は、成熟した大人になるということをキーワードに、80年生きてきた著者がその経験から得た気付きを綴ったエッセイ集です。人間関係に疲れた時、自分らしく生きるとは何かを見失った時、この本はそっと背中を押してくれます。
「自分を大切にする人は、人も大切にできる」
「自分の生まれ持った性質通りに生きる」
「いい言葉を使う人にはいい人生をつくる力がある」
「自分に厳しく、人に優しく、もう一巡して自分にはもっと優しく」
これらの言葉に触れ、他人の評価ではなく自分の軸で生きることこそが幸せなのだと気付かされました。この本は自分を見つめ直すきっかけを与えてくれる、そんな一冊です。
法学部4年生 北島 京香
『世界中から人が押し寄せる小さな村 : 新時代の観光の哲学』
島村菜津[著] 光文社 2023年
瀬田図書館:本館2F開架 689.237/シナセ
資料番号:32305045785
あなたは、観光においてどのような体験を求めますか?
近年、世界ではマスツーリズムの発展により、様々な観光地でお土産物の画一化や観光地のテーマパーク化などが発生する、観光地の均質化が発生しています。あなたも、観光地の「そこである必要性」が薄れてきていると感じたことはないでしょうか?
本書は、そのようなマスツーリズムとは相反する、新時代の観光形態「アルベルゴ・ディフーゾ」について、発祥の地、イタリア南部の小さな村を舞台に、観光のあり方を問い直す一冊となっています。
人気の土産物屋を呼び込むのではなく、「本物」に徹底的にこだわることで地域の文化を守り、地域内雇用を生む。アルベルゴ・ディフーゾは、単なる観光形態の話ではなく、過疎化する地域の地域振興といった面も強く持っています。
皆さんも、自分の地域に眠っている価値とは何なのか、どのような文化を守っていく必要があるのか、本書を通して今一度考えてみませんか?
政策学部3年生 内 世理
オルダス・ハクスリー[著] 黒原敏行[訳] 光文社 2013年
深草図書館:和顔館2F開架文庫・新書 081/コウフ/1Aオ2-1
資料番号:11300037937
瀬田図書館:本館1F文庫 081/コウフ/Aオ-2-1
資料番号:31305038650
西暦2540年、幾度の核戦争を経た人類は、安定至上主義の社会を築き上げていた。出生が完全に管理される世界で、大量生産される人間はセンターで教育され、5つの階級に合った生き方をコントロールされる。
遺伝子の選別、飲むだけで多幸感を得られる快楽薬ソーマの配給、幼少期からのフリーセックスの推奨、睡眠学習による「条件づけ」と呼ばれる洗脳教育など、誰もが決められた人生を幸福に生きる。「家族」は恥ずべきものとされ、老いることもなく、死への恐怖も消された文明社会に、突然未開の地「蛮人保護地区」から連れてこられた一人の青年が、文明社会で騒動を巻き起こす。
「家族」を持ち、神を信じ、死を恐れる彼は、徹底管理された「幸せ」に満ちた文明社会に何を思うのか。「自由」とは、「人間らしさ」とは一体何なのか。発表以来、多くの読者に議論され続けてきた、ディストピア小説の名作。
国際学部3年生 松下 日咲
江戸川乱歩[著] 角川書店 2008年
瀬田図書館:本館B1開架 913.6/エラエ/1
資料番号:31700014682
「私はお化けのような顔をした、その上、ごく貧乏な、一職人に過ぎない私の現実を忘れて、身の程知らぬ甘美な、贅沢な、様々様々の「夢」にあこがれていたのでございます。」
江戸川乱歩 『人間椅子』
貧しい椅子職人は、世にも醜い容貌のせいで、常に孤独だった。惨めな日々の中で思い詰めた男は、納品前の大きな肘掛け椅子の中に身を潜める。その椅子は、若く美しい夫人の住む立派な屋敷に運び込まれて…。
椅子を介して夫人への想いを募らせる男の偏愛を著した作品に始まり、江戸川乱歩の傑作品ともいえる刺激的な作品が収録された一冊となっています。緻密なトリックと奇抜な設定が特徴の江戸川乱歩。不可思議な人間関係や風変わりな登場人物たちによって織りなされる各作品は、きっと、読者を夢中にさせてくれます。
生誕130年を迎える今年、推理小説の礎を築いた、江戸川乱歩を近くに感じてほしいです。
社会学部4年生 筏津 一心
宮下奈都[著] 文藝春秋 2015年
深草図書館:和顔館2F開架 913.6/ミナヒ
資料番号:11905018882
瀬田図書館:本館地下1階 913.6/ミナヒ
資料番号:31605033161
皆さんは調律師という言葉を聞いたことはありますか?調律師とはピアノなどの楽器の音律を調整する仕事のことで主に音程を正確に合わせたり、音色を調整したりすることを指します。
この本の主人公である外村はある日、担任の先生に来客の案内をするように頼まれます。その来客が調律師の板鳥という人物でした。外村は板鳥と出会い、初めて調律師の仕事を体験し、だんだんと調律師という仕事にあこがれを抱いていきます。そこから外村は調律師を目指すため、たくさん調律についての勉強をしていき、板鳥のいる職場で一緒に働くようになります。この本では外村は板鳥との出会いがきっかけで調律師になりたいという夢ができ、人として成長していく物語です。
私はこの本を読んで板鳥との出会いで、調律師という仕事にあこがれ、その夢に向かって全力で努力する外村がとても印象的でした。みなさんもこの機会にぜひ読んでみてください。
先端理工学部4年生 浅田 泰斗
三秋縋 [著] KADOKAWA 2013年
深草図書館:和顔館2F開架学生選書 081/2021/53
資料番号:12100021981
あなたは今までにどのような人生を歩んできただろうか。それは、恐らく長いようで短い道のりであっただろう。その道中で、生きることに辛さを感じたことはなかっただろうか。ある人は今までの人生を悔い、またある人はこれからの人生に不安を覚える。もし、これからの人生に望みがなくなった時、自分の人生を売却できるとしたら、あなたの歩むはずだった人生は一体いくらになるだろうか。
平均的な生涯年収は3億円であるという話はどこかで聞いたことがあるだろう。多くの人はこの話を元に自分の人生の価値について考えるだろう。しかし、いざ自分の人生の価値を売却しようとしたとき、想像より低い価格だった場合、あなたはどう考えるだろうか。
不幸にも1年につき1万円の値段がつけられた時、自分の人生につけられた値段についてどう思うだろうか。あきらめず人生を歩み続けるだろうか。それとも、人生を売ってしまうだろうか。
農学部3年生 佐藤 萌空
小川洋子[著] 中央公論新社 2011年
瀬田図書館:本館B1開架 913.6/オヨヒ
資料番号:31105041422
日本ではない、どこか遠い国で起きたテロ事件に巻き込まれてしまった八人の人質たち。人質事件のニュースを聞いた人々が、事件が起きていることさえ忘れかけるほどの長い時間が経っていく。その中で、人質たちはひっそり、思い出の朗読会を開いていた。一人が丁寧に書きだした思い出を語る間、ほかの七人はそっと耳を傾けている。彼らの何気ない日常に潜んだ不思議な体験の朗読会は、犯人にだって邪魔することはできなかった。
本書は、八人の人質たちそれぞれの思い出が語られた短編集です。話し手の心理描写が細かく、物語の中に入り込みやすいため、普段小説に馴染みがない人でも読みやすい本です。また、人質たちのような不思議な体験はしていなくとも、不思議と共感できる部分が多いのも特徴です。読後は静かな安らぎが貴方の身を包むでしょう。ぜひ手に取ってみてください。
短期大学部2年生 櫻井 葵